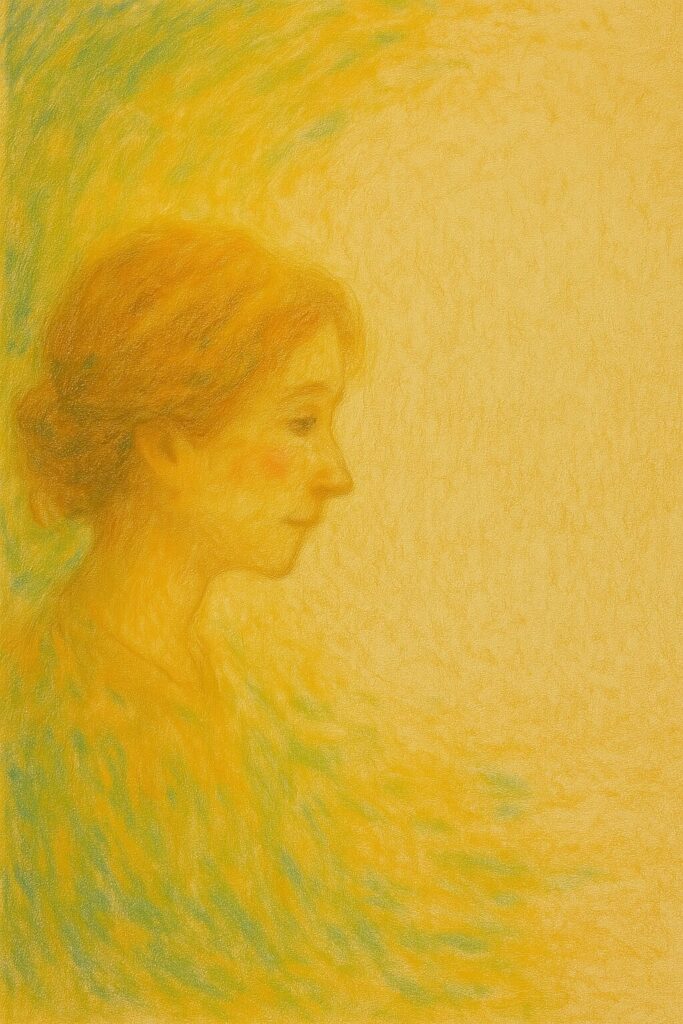【まなざしの先に】 第10話:
ロバ隊長を知っていますか?──問いかけがひらくまなざし
〔モノローグ〕
気がつけば、問いかけることを忘れていた。
知ってもらうことが目的になって、
その先に何を望んでいたのか、立ち止まって考えたことがあっただろうか。
わたしが届けたかったのは、
ロバ隊長の名前ではなく、
まなざしのその先にある、小さな声に気づく感性だったのかもしれない。
2025年7月、なかはらっぱ祭りの一角で「ロバ隊長を知っていますか?」という問いをテーマにシール投票を実施しました。これは、昨年の「なかはら福祉健康まつり」に続く第二弾の取り組みです。
今回の投票では、親子連れをはじめとする地域の方々が足をとめ、大きな模造紙の問いに、星形のシールを貼ってくれました。
投票結果を見ると、「知らない」と答えた方は51人。「知っている」は27人。ほとんどの方が、”ロバ隊長”という存在に触れるのは初めてだったようです。
けれど、その場にいた誰もが、どこかで笑顔になっていました。小さな子どもがロバ隊長のイラストを指さして「かわいい」とつぶやいたり、お年寄りの方が「こんな取り組みがあるのね」と感心されたり。愛らしいロバ隊長のイラスト、親しみやすい問いかけ、そして、そこに込められた想いを静かに受け取ってくださったのでしょう。
—
参加者の声には、印象的なものがいくつもありました。
・ボランティアに来ていた高校生から
「いままで認知症について学んだことがなかった。授業でも扱われたことがない」
・認知症サポーター養成講座の受講経験者数名から
「ロバ隊長って、麻生区の認知症啓発のマスコットだと思っていた」
この言葉に、わたしははっとさせられました。そもそも、なぜロバ隊長の存在を知ってもらいたかったのか。この問いに対して、自分なりの明確な視点を持たずにいたことに気づかされたのです。
ロバ隊長の目的は何なのか──
まちなかで困っている認知症の方に、さりげなく寄り添うしるしなのか。
それとも、サポーター講座を受けた人が”証”として身につける目印なのか。
あるいは、その両方を内包した、”まなざし”の象徴なのか。
わたし自身、そのビジョンを明確に持たないまま、「知っているか・知らないか」の認知度ばかりに意識が向いていたのです。
地域包括ケアシステムのなかで、ロバ隊長が果たす役割とは何か。認知症サポーター養成講座と、どう結びつけていくのか。そして、まちなかで本当にSOSがキャッチされるためには、何が必要なのか──この問いを、投票を通して真正面から向き合うことになりました。
—
さらに、ロバ隊長を知ってもらうことは、”ヤングケアラー”の存在とも静かにつながっていると感じました。
ヤングケアラーは、子どもから30代(40歳未満)までの若い世代が対象です。家族の介護や看病、支援のために、日常生活の多くを担っています。そのなかには、自分が”ケアラー”であることにすら気づいていない人も少なくありません。
昨年の福祉健康まつりでは、「ヤングケアラーを知っていますか?」というアンケートを実施しました。そのとき聞かれた声のひとつに、こんな言葉がありました。
「親の勉強不足。どこに相談していいのか分からない。自身が困っていることを言い出せない。困っていることに気がつかない」
これは、支援の手を差し伸べていても、その手を取ることができない現実と、まさに表裏一体の関係です。スティグマ(偏見)という見えない壁が、支援と孤立のあいだに立ちはだかっているのです。
だからこそ、こどもの頃から「頼れる場所」があること、「学んでいい・相談していい」という空気が社会のどこかにあることを、”ロバ隊長”という親しみある存在がそっと伝えてくれるような、そんな場を育てていきたいと思います。
—
「ロバ隊長を知っていますか?」
その問いを通して、わたし自身が受け取ったのは、認知度の数字ではありませんでした。”知らないこと”を受け入れる人のまなざし、そして”知ってもらいたいと願う側”の問い直し。そこにこそ、本当の価値があったのです。
問いの先に、また新たな問いが生まれる。そうして、一歩ずつ、まちとわたしたちの関係性も育っていくのかもしれません。