2025年7月の竹内先生のコラム(お手紙)です。自筆を大切にしたいので、ファイルを張り付けています。
竹内先生のコラムPDF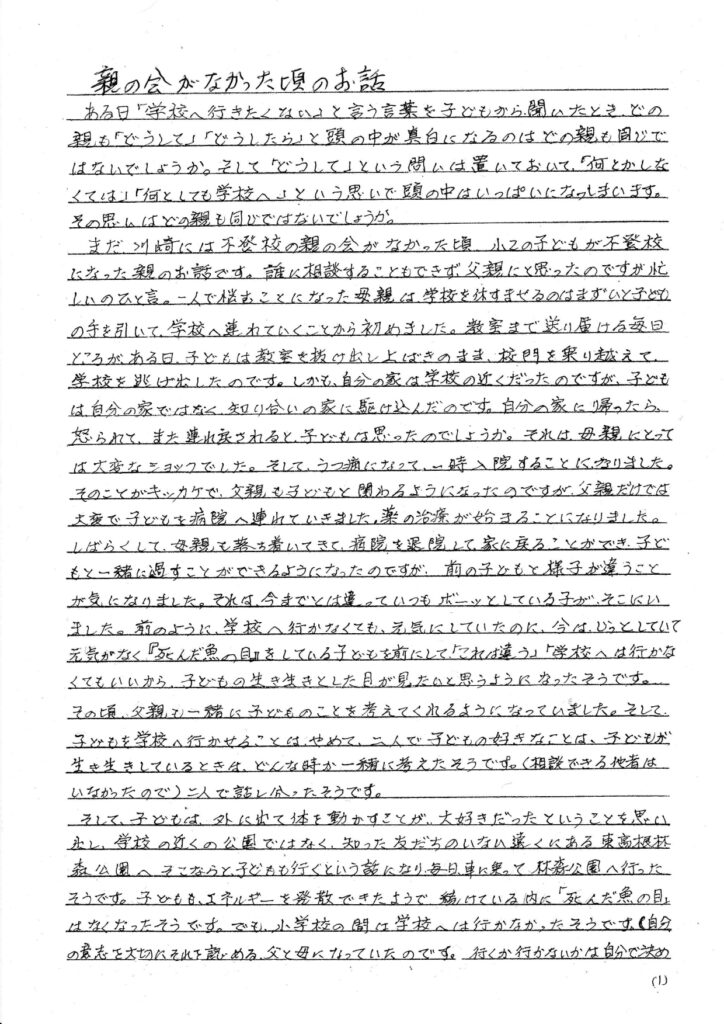
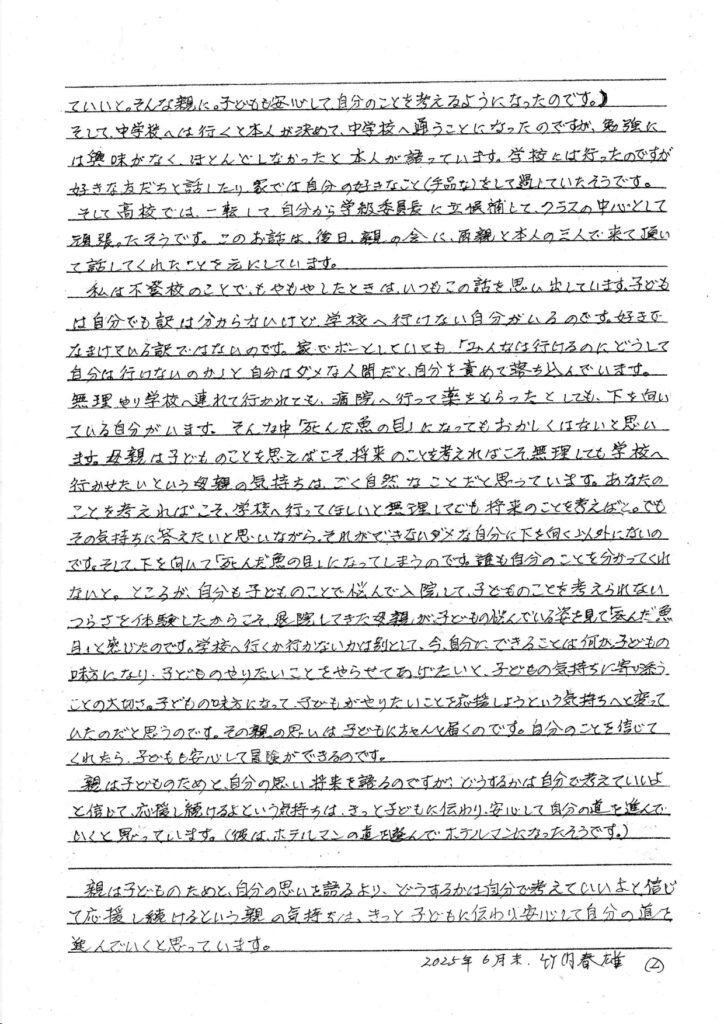

— 以下テキスト版 —
親の会がなかった頃のお話
ある日「学校へ行きたくない」と言う言葉を子どもから聞いたとき、どの親も「どうして」「どうしたら」と頭の中が真白になるのはどの親も同じではないでしょうか。そして「どうして」という問いは置いておいて、「何とかしなくては」「何としても学校へ」という思いで頭の中はいっぱいになってしまいます。その思いはどの親も同じではないでしょうか。
まだ川崎には不登校の親の会がなかった頃、小2の子どもが不登校になった親のお話です。誰に相談することもできず父親にと思ったのですが忙しいのひと言。一人で悩むことになった母親は学校を休ませるのはまずいと子どもの手を引いて、学校へ連れていくことから初めました。教室まで送り届ける毎日。ところが、ある日、子どもは教室を抜け出し上ばきのまま、校門を乗り越えて、学校を逃げ出したのです。しかも、自分の家は学校の近くだったのですが、子どもは、自分の家ではなく、知り合いの家に駆け込んだのです。自分の家に帰ったら、怒られて、また連れ戻されると、子どもは思ったのでしょうか。それは、母親にとっては大変なショックでした。そして、うつ病になって、一時入院することになりました。そのことがキッカケで、父親も子どもと関わるようになったのですが、父親だけでは大変で子どもを病院へ連れていきました。薬の治療が始まることになりました。しばらくして、母親も落ち着いてきて、病院を退院して、家に戻ることができ、子どもと一緒に過すことができるようになったのですが、前の子どもと様子が違うことが気になりました。それは、今までとは違っていつもボーッとしている子が、そこにいました。前のように、学校へ行かなくても、元気にしていたのに、今は、じっとしていて元気がなく『死んだ魚の目』をしている子どもを前にして、「これは違う」「学校へは行かなくてもいい」から、子どもの生き生きとした目が見たいと思うようになったそうです。
その頃、父親も一緒に子どものことを考えてくれるようになっていました。そして、子どもを学校へ行かせることはやめて、二人で子どもの好きなことは、子どもが生き生きしているときは、どんな時か一緒に考えたそうです。(相談できる他者はいなかったので)二人で話し合ったそうです。
そして、子どもは、外に出て体を動かすことが大好きだったということを思い出し、学校の近くの公園ではなく、知った友だちのいない遠くにある東高根林森公園へそこならと、子どもも行くという話になり、毎日、車に乗って、林森公園へ行ったそうです。子どもも、エネルギーを発散できたようで、続けている内に「死んだ魚の目」はなくなったそうです。でも、小学校の間は学校へは行かなかったそうです。⦅自分の意志を大切にそれを認める父と母になっていたのです。行くか行かないかは自分で決めていいと。そんな親に。子どもも安心して、自分のことを考えるようになったのです。⦆
そして、中学校へは行くと本人が決めて、中学校へ通うことになったのですが、勉強には興味がなく、ほとんどしなかったと本人が語っています。学校には行ったのですが好きな友だちと話したり、家では自分の好きなこと(手品な)をして過していたそうです。
そして高校では、一転して、自分から学級委員長に立候補して、クラスの中心として頑張ったそうです。このお話は、後日、親の会に、両親と本人の三人で来て頂いて話してくれたことを元にしています。
私は不登校のことで、もやもやしたときは、いつもこの話を思い出しています。子どもは自分でも訳は分からないけど、学校へ行けない自分がいるのです。好きでなまけている訳ではないのです。家でボーとしといても「みんなは行けるのにどうして自分は行けないのか」と自分はダメな人間だと、自分を責めで落ち込んでいます。無理やり学校へ連れて行かれても、病院へ行って薬をもらったとしても、下を向いている自分がいます。そんな中「死んだ魚の目」になってもおかしくはないと思います。母親は子どものことを思えばこそ、将来のことを考えればこそ、無理しても学校へ行かせたいという母親の気持ちは、ごく自然なことだと思っています。あなたのことを考えればこそ、学校へ行ってほしいと無理してでも、将来のことを考えねばと。でもその気持ちに答えたいと思いながら、それができないダメな自分に下を向く以外にないのです。そして、下を向いて「死んだ魚の目」になってしまうのです。誰も自分のことを分かってくれないと。ところが、自分も子どものことで悩んで入院して、子どものことを考えられないつらさを体験したからこそ、退院してきた母親が、子どもの悩んでいる姿を見て「死んだ魚の目」と感じたのです。学校へ行くか行かないかは別として、今、自分にできることは何か。子どもの味方になり、子どものやりたいことをやらせてあげたいと、子どもの気持ちに寄り添うことの大切さ。子どもの味方になって、子どもがやりたいことを応援しようという気持ちへと変っていたのだと思うのです。その親の思いは子どもにちゃんと届くのです。自分のことを信じてくれたら、子どもも安心して冒険ができるのです。
親は子どものためと、自分の思い将来を語るのですが、どうするかは自分で考えていいよと信じて、応援し続けるよという気持ちは、きっと子どもに伝わり、安心して自分の道を進んでいくと思っています。(彼は、ホテルマンの道を選んでホテルマンになったそうです。)
親は子どものためと、自分の思いを語るより、どうするかは自分で考えていいよと信じて応援し続けるという親の気持ちは、きっと子どもに伝わり、安心して自分の道を進んでいくと思っています。